
バーチャルサラウンド7.1chって何なの?
FPSやるならやっぱりないとダメかな?
こういった疑問についてお答えしていきます。
バーチャルサラウンドを実際に使用してFPSやバトルロワイヤルゲームをやっている私が、バーチャルサラウンドについて詳しくお伝えしていきます。

今回この記事を書いたのはネットの記事にバーチャルサラウンド7.1chは必要ないという意見が多くあり、その意見を言っている方の使用環境もわからないまま否定されていて残念な記事ばかり・・・。
そこで、色々なゲーミングヘッドセットやサウンドカードを使用している私が詳しくバーチャルサラウンド7.1chについてお伝えしていこうと思い今回の記事を書く経緯となりました。
今回この記事では
- バーチャルサラウンド7.1chについて
- バーチャルサラウンド7.1chのメリット・デメリット
- バーチャルサラウンド7.1chを使用する方法
上記の3点について詳しく書いていきます。
では「バーチャルサラウンド7.1chは必要か?メリット・デメリットを紹介」について書いていきます。
バーチャルサラウンド7.1chについて
実際に使用したことがない方はどういった感覚で聞こえてくるのか分からないと思いますので、詳しく書いていきます。
上記画像の通りの仮想空間を作り出し、周囲の7つのスピーカーから音が聞こえてくるかのような機能になります。
.1は重低音を得意とするサブウーファーのこと。
なので、7つのスピーカー + サブウーファー = 7.1ch となります。
7つのスピーカーから聞こえてくる形となるので、音の位置を把握することができたり、音の距離感などもわかりやすくなります。
ちなみに、リアルサラウンドというものもありますがそちらについてはプルダウンで詳しく解説しておりますので、気になる方は開いてみてください。
リアルサラウンドとはその名の通りスピーカーを7つ周囲に置くことでリアルサラウンドを使用することができます。
ゲーミングヘッドセットにもスピーカーが多数付いていて多chのリアルサラウンドを実現している物もあります。
しかし、リアルサラウンドの現状のほとんどが音の位置を掴みにくかったりとFPSなどのゲームには向いていない。
こうした現状からバーチャルサラウンドがゲームでは上回っているのでリアルサラウンドについては今回は説明を省きました。
バーチャルサラウンド7.1chを説明するのにメリットとデメリットで詳しくお伝えしていきます。
バーチャルサラウンド7.1chのメリット・デメリット
バーチャルサラウンド7.1ch(疑似7.1ch)を使用することでのメリットとデメリットをお伝えしていきます。
- 音の情報が多く、広がりがあるので音の位置を把握しやすくなる
- ステレオ(2ch)は左右しかわからないが、疑似7.1chは立体的で上下前後もわかる
- ゲームにおいては音の位置の表現に向いている
- 音をワイドに聞き取るので音が小さい場合がある
- 人によって相性がありバーチャルサラウンド7.1chでも音の位置を把握できない
- メーカーによって前後の音の定位が悪かったりなどする
バーチャルサラウンド7.1chのメリット・デメリットについてはバーチャルサラウンド7.1chを提供しているメーカーによって変わってきてしまうので、参考程度に見てください。
バーチャルサラウンド7.1chは定位が重要
上記でメリット・デメリットを述べた通り全て音がしっかりと聞けて音の位置を把握できるかという点にあります。
メーカーによってバーチャルサラウンドの技術が違ってきます。
主にゲーミングデバイス(ゲーミングヘッドセットやサウンドカード)で取り入れられているのはドルビーの「DTS HEADPHONE:X」などの技術を導入していることが多いです。
独自のバーチャルサラウンド技術を使用しているのはHyperXやCreativeのSoundBlasterシリーズとゼンハイザーのGSX1000などです。
特筆しておきたいのがSENNHEISERのGSX1000はバイノーラル技術といった、人間の頭部の音響効果を再現するダミーを利用してリアルな臨場感を再現します。
この様に、それぞれメーカーによって違ってくることがありますので、バーチャルサラウンド目的で購入をする際は音の定位を気にして選びましょう。
私にも失敗例があり、CreativeのSoundBlasterシリーズのバーチャルサラウンド7.1chは前後の定位が悪く、FPSなどのゲームで後ろから撃たれたのかも把握できないことがありました。
最近になってSoundBlasterX G6やSoundBlaster AE-9が最新のサウンドカードとして出てきましたが後ろの定位が悪いというレビューが多くまだまだサウンドブラスターシリーズのバーチャルサラウンドはFPSには向いていないなと思います。

Creativeのサウンドブラスターシリーズはアマゾンでランキング上位に多数ありますね。
こういった定位の悪いサウンドカードを使用してバーチャルサラウンド7.1chは微妙だよと一括りにしている意見を多く見て残念に思います。
バーチャルサラウンド7.1chを使用する方法
バーチャルサラウンド7.1chを使用するには大きく分けてハードウェアの導入かソフトウェアで制御に分けられます。
- サウンドカード
- USB-DAC
- Windows Sonic Headphone
- Razer Surround
それぞれどういった物かを紹介していきます。
USB-DAC
USB-DACはUSB端子で外付けのDACでデジタル信号からアナログ信号へ変換する。
ゲーミングヘッドに付属で付いてくる物もUSB-DACと呼びます。
PCにもDACの機能はあるがマザーボードや電源にはノイズが多く、変換時にノイズが入る。
そういったことから外付けのDACで変換することでノイズなどの影響が受けにくくなる。
USB-DACを使用することで専用のソフトウェアなどで制御してバーチャルサラウンド7.1chの機能を使用することを可能にしています。
サウンドカードと比べると安価だが、ノイズなどの音質面は劣る。
DACや音に関する詳しい解説は「【FPS】ゲーマーに伝えたいサウンドとデバイス構成について【サウンドカード】」で紹介していますので参考にしてください。
サウンドカード
サウンドカードはUSB-DACと同じく、DACの機能がありデジタル信号からアナログ信号へと変換する。
USB-DACと比べて音質が良く、ノイズがほとんどない物が多い。
メリットが多くある分価格も高いです。
USB-DACよりも本体での操作や調整を可能としている物が多くありますね。
サウンドカードはハードウェアとソフトウェアの両面で調整や操作ができます。
より良い環境でバーチャルサラウンド7.1chの機能を使用したいのであればサウンドカードがおすすめです。
FPSにおすすめなサウンドカードは「【2019年5選】FPSでおすすめのサウンドカード【コスパ重視】」にて紹介しております。
Windows Sonic Headphone
Windows10から標準で付いてくる機能「Windows Sonic Headphone」です。
設定自体も簡単に設定できるが、あまりよくはないと感じたのであまりおすすめはできない。
一応無料で立体音響を使用するほうほうとして「お金をかけずにバーチャルサラウンド7.1chにする方法」で詳しいことは参考にしてみてください。
実際にPUBGで試してみたところ、後ろの音が強調されて前が弱い、全体的にこもったような音になり低音域が聞き取りにくいと感じました。
Razer Surround
Razerの公式サイトからインストールして使用することができるソフトウェア「Razer Surround」。
有料のPRO版が無くなり、無料サービスのみが残った状況で、Razer製品を持っていれば無料でPRO版と同じことができるようになる。

要は物を買えってことですね。
私の環境では試すこともできなかったので、どういったソフトウェアでのバーチャルサラウンド7.1chになるのかはお伝え出来ず残念です。
気になる方は上記URLからインストールしてみてください。
DTS Sound Unbound
30日間の無料トライアルから有料の2,500円支払うことでドルビーのサラウンドを使用することができる。
ドルビーのDTS HEADPHONE:X 2.0が使用できるので魅力的ではあるが、2,500円は高いのではないかと思います。
定位はしっかりとしていてドルビーは安定して定位が良いなと感じます。
結論:定位が良ければ何でも大丈夫
しっかりとFPSで足音が聞き取れれば環境なんてなんでもいいんですよね。
もちろんバーチャルサラウンド7.1chを使用しなくても音の定位を掴めるのであれば必要ないですね。
私個人のおすすめとしてはゲーミングヘッドセットで始めて、もっと良い環境にしたければサウンドカードを導入するといった形にしていけば良いのではないのかと思います。
絶対に何かが必要というわけではなく、FPSで足音の位置を正確につかむには何が必要なのかといったところを重要視して選んでいただければ大丈夫です。

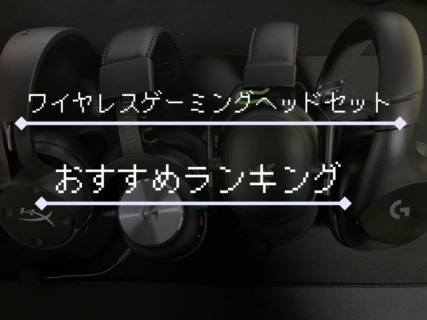






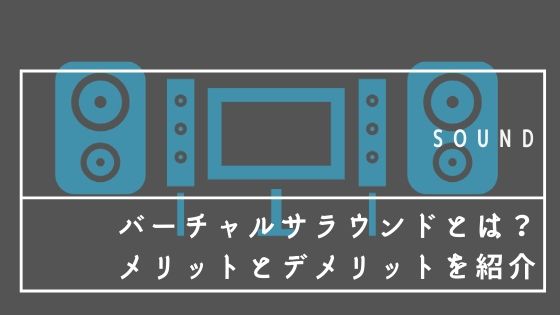



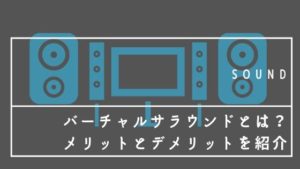
コメント